![]()
![]()
名匠ロバート・T・ジョーンズの愛弟子の一人がマイケル・ポーレット。
彼が手がけたのが、リンクスの思想が随所に溢れるカレドニアンである。
選・文/大塚和徳
![]()
グリーン周りの難しさに定評のある415ヤードの9番パー4。
フェアウェイのうねり具合にリンクスのエッセンスがたっぷりうかがえる。
カレドニアン・ゴルフクラブは千葉県の中央部に位置し、東関東自動車道の富里ICから約20分、千葉東金道路の松尾横芝ICから数分の地にある。バブル経済末期の1990年に開場。バブル期には何人ものアメリカ人設計家が来日して大金を投じたコース造りを行い、ゲーム上意味のない奇を衒ったハザードやグリーンで目を惹こうとしたが、多くは本流から外れていた。しかし、カレドニアンは違う。マイケル・ポーレットが経験・知識のすべてを投じて設計し、その成果を世に問うた傑作である。
生まれは1943年。大学で植物学、大学院で造園学と芝草の管理を学んだポーレットは、1970年代初期、コース設計家ロバート・T・ジョーンズと出会い、彼のアジア事務所を任された。ここで約20コースの設計・建設を経験。その後、英国で有名リンクスを中心に多くのクラシックコースを実地に調査・研究し、設計の糧とした。一時、アイオワ州立大の先輩ディック・フェルプスの事務所でコロラド州をベースに活躍したが、カレドニアン建設時には独立していた。
ポーレットがカレドニアンで目指したのは、変化に富んだ挑戦的で個性的な18ホールがバランス良く配置され、周囲の景観に溶け込んだ美しいリンクス風のコースだった。
確かにこの設計思想は十分に実現されている。ルートプランでは原地形が上手に生かされ、バンカーとマウンドを軸にしたハザードは正にリンクス風である。変化に富んだ各ホールは、いずれも違ったコンセプト。グリーンの多くは長方形で細長く、飛球線から捩じれて斜めに横たわる。長方形でないものも、通常の円形ではなく、クラシックな四角形のバリエーションである。表面のアンジュレーションもいわゆる“ポテトチップス”ではない。原地形の傾斜を大胆に生かした、英国で“マッケンジー・グリーン”(アリスター・マッケンジーにちなんで)と呼ぶものに近い。なかでもいくつかのグリーンは「戦略型設計」の元祖ジョン・ローが推奨した、後方へ下る形状となっている。
グリーン周りには深さのある“アリソン・バンカー”が多いが、4番パー4ではフェアウェイ右半分を覆って同形のものが現れ、レイアップするか越えるか、左へ避けるかの選択を迫る。フェアウェイのサイドバンカーにも変化をつけ、14番パー4ではポットバンカーを使っている。フェアウェイのハザードでは、16番パー4でボストンの超名門マイオピア・ハントCで有名なチョコレート・ドロップに出合う。さらにリンクスの有名ホールの応用例が随所に出てくる。17番パー3は有名な「レダン」、続く18番パー5は出だしが大きな池を使った「ケープ」で、アプローチは美しいビーチバンカー越えだが、左からの迂回ルートも用意されている。
当クラブのモットーは、ロイヤル・トゥルーンGCと同じ“Tam Arte Quam Marte”(As much by skill asby strength)「力と同様に知略で」という意味である。コース征服にはこの言葉通りに、正確なショットを打てる技術が求められる。
リンクス風の素晴らしさから連想するのは、2007年夏に訪ねたキングズバーンズGCである。数年前にセント・アンドリュースの東に誕生して話題を呼んだこのコースは、同じジョーンズ事務所の欧州代表だったカイル・フィリップスの傑作。それゆえに、アジア事務所の代表だったポーレットの傑作カレドニアンは、“日本版「キングズバーンズ」”と呼びたい。
![]()
題字・イラスト/小寺茂樹
※この記事では、名門コース(D =distinguished)、クラシックコース(C =classical)、隠れた宝石コース(H =hidden gem)、モダン・アメリカンコース(M =modern American)の4タイプに類別して紹介します。
「GOLF TODAY」2011年4月号466号より
時代的背景によるコース・カテゴリー化とそれぞれの名コース
本流の思想にジョーンズとポーレット独自の思想がカレドニアンの設計に生きている
大塚 和徳(ゴルフ史家)
![]()
![]()
カレドニアン・ゴルフクラブNo.16
「モダーン・アメリカン」の一人、カレドニアンGCの設計者マイケル・ポーレットは三代続くゴルフ一家に生まれ、12歳でゴルフを始めた。3つの大学でそれぞれ生物学、芝草、造園学を専攻して学位をとり、ロバート・ジョーンズとの出会いからコース設計へ足を踏み入れた。
ポーレットの設計概念は、基本にアメリカン・ゴルフの本流ロバート・トレント・ジョーンズの思想があり、更には独自に学んだイギリスの古典派思想、アメリカの近代設計思想が加味された固有のものである。
“カレドニアン”はネーミング(“カレドニア”はローマ人が使った“スコットランド”を意味する古語)も素晴らしいが、コースも本場リンクスの雰囲気を持ったポーレットの代表作であり、その個性的な設計は名作の域に十分達している。
日本のコース・ランキングでは、戦前から続くアリソン流の「ジャパニーズ・クラシック」と、ここで論じた「モダーン・アメリカ」とが多くを占める。これは極めて順当である。二つは全く違った設計思想で、その優劣は論じ難いが、確かな設計理論に支えられた“優れたコース”である点は同じである。「ジャパニーズ・クラシック」には母国イギリスから続く本流の良さが、「モダーン・アメリカン」にはイギリス流にはない“近代性”、“豊富なアイディア”、“奇抜な発想”が見受けられる。
最近、スコットランドやアイルランドにアメリカ型リンクスが誕生しているが、これは「アメリカ型」が本物であることの証拠であろう。
![]()
【プロフィール】
ゴルフ史家。
1934年、大分県生まれ。東京大学経済学部卒業後、第一銀行を経て帝人に入社。ウォートン・スクールでMBA取得。英国ターンベリーホテルの経営、ジ・オックスフォードシャーGCの建設に携わる。海外で回った有名コースは350を超え、現在は米ゴルフマガジン誌「世界ベスト100コース」の選定パネリスト。英国ロイヤル・ノースデボンGC会員。〈主な著書〉『ゴルフ五番目の愉しみ』(文春新書)、『「ゴルフ千年」― タイガー・ウッズまで』(中公新書ラクレ)がある。
![]()
カレドニアン・ゴルフクラブNo.17
リンクス魂を継承するグリーン
文/西澤 忠
千葉県の成田空港にほど近く、やがて開場して四半世紀を迎え、2000年には「日本プロ選手権」を開催した(佐藤信人優勝)ユニークなコースがある。スコットランド国名の古語を名称にした『カレドニアンGC』で、J・マイケル・ポーレット(John Michael Poellot 1943~)のレイアウトはスコットランド・リンクスの魂を受け継ぐ設計手法で、造形も戦略もかつての日本にはなかったスタイル。つまり、従来の日本的な“平坦なフェアウェイの林間コース”ではない。地表はうねり、変幻自在な形のグリーンが池を伴って佇むからで、それは、ポーレットがペンシルべニア州生まれの米国人だが、バタ臭い米国式デザインを避けて英国式リンクス志向を目指したから。その手腕を買われて最近では、トム・ファジオと組んで『プリザーブGC』を造り、全米100コースの81位にランクされている。
彼の特徴として、対角線設計(diagonal design)がある。プレイヤーが狙うターゲット(目標)のフェアウェイやグリーンを対角線上に置くという方式。池でもバンカーでもターゲットをガードするハザードはプレイヤーに正対せず、斜めになるので、距離と方向の両方をテストされる。
したがって、スコットランドの古い名リンクス、『ノースベリックGC』15番、愛称“レダン”を模したホールがあるのは当然であろう。
『カレドニアンGC』では17番(195ヤード・パー3)がそれだ。大詰めにあるホールは谷越えになるグリーンが縦長で、左側には深いバンカーが2個、右側には一段低いラフ・エリアになる。手前3分の2は単なる受け勾配だが、心憎いのはその先に左右に尾根(Ridge=分水嶺)が走り、奥に下る勾配が微妙に左に傾く。ホールの中心線に対して約45度左に振れたこの部分に旗の立つときは難度が著しく上がり、まさにレダン・タイプの戦略が浮き上がる。本場のレダン・ホールはマウンド越しのブラインド・ホールだが、
ここは明確にボールの行方が見える。それだけに、プレッシャーは倍加する。ドロー・ボールを打ちたいが、左のハザードが気になる。この緊張感が堪らない。距離の短い曲者のパー4が16番、そして最終18番は二度も池を越すパー5ホールで、変幻自在な上り3ホールがドラマを演出する。
まさに見事なフィナーレの舞台設定ではないか。
コース設計家という創造者にはゴルフ史の古典に学んだ“温故知新”の心意気があるのだろう。
![]()
にしざわ ただし/ゴルフジャーナリスト。
1941年生まれ。1965年早稲田大学文学部西洋哲学科卒。同年、ゴルフダイジェスト社入社。同社発行の月刊「ゴルフダイジェスト」誌編集長を経て、1996年1月にゴルフジャーナリストとして独立。
REDAN誌 2015年11・12月号より
記事一覧に戻る




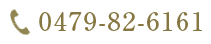




 カレドニアン・ゴルフクラブNo.16
カレドニアン・ゴルフクラブNo.16

 カレドニアン・ゴルフクラブNo.17
カレドニアン・ゴルフクラブNo.17
