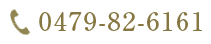4月は世界中のゴルフファンが待ちに待ったメジャー最高峰のマスターズが開幕する。天国もかくやと思われる美しいオーガスタ・ナショナルで繰り広げる世界のトップゴルファーたちの妙技。その面白さを引き出すのは、ガラスの上の転がりと表現される14 フィートの超高速グリーンや、池、クリークが行く手を阻む難度の高いコースに他ならない。最後まで息をつかせぬスリルに富んだ戦いを演出するのは、この最高の舞台があってこそ。テレビを見るたびに日本のファンは「所詮別世界での出来事」と諦めている。だが日本にもこのオーガスタに勝るとも劣らないコースがあることをゴルファーは知っているだろうか。そのコースこそ日頃名コースとして評判のカレドニアン・ゴルフクラブ(千葉県)である。
 短いパー4ホールでは、世界トップレベルと評価された13番と対岸の18番グリーン(パー5)
短いパー4ホールでは、世界トップレベルと評価された13番と対岸の18番グリーン(パー5)

2014年日本中を驚かせた超高速14フィートへのチャレンジ
2014年4月、ゴルフ業界やゴルフに携わるマスコミ人の間で衝撃的な話題が持ち切りになった。カレドニアンGCが「オーガスタ・ナショナルに匹敵する14フィートの超高速グリーンに挑戦する」というニュースが駆け巡ったからだ。14フィートといえば、世界最高レベルの米国ツアーでも、マスターズのオーガスタ・ナショナルぐらいしか聞いたことがない。日本では「実現不可能」な夢物語でしかないと思われていた。
ちなみに高速グリーンというとプロ競技の専売特許で、最も速い米男子ツアーで平均12フィートから13フィート。日本の男子ツアーが10~12フィート、女子ツアーが9.5~11フィートと言われている。つまりカレドニアンGCは米男子ツアーに匹敵するスピードで一般営業という奇跡のような体験をさせてくれるコースなのである。
日本のプロツアーの場合、高速グリーンといっても急造のケースが多い。試合期間に合わせて、芝を短く刈り、ローラーで固める。これで通常より速くなることは確かだ。だが急造のグリーンはストレスもかかり、芝を傷める。ベントの芝はそれほどデリケートなのだ。
ところが、そんな中でカレドニアンGCは、競技とは関係なく、通常の営業で14 フィートに挑戦するというのだから、その驚きはまたたくうちに全国に広まっていった。
これまで経験したことのない速さの上に、まるで最高級の絨毯のように手入れされた密度の詰まった芝の上を、ボールが滑るように転がっていく。多くのゴルファーがこの異次元の感覚を味わったのはその後の評判が証明している。これまでの計測では、最高14.6フィートを出しているという。
日本では不可能とされたガラスの上を転がるようなグリーンを実現させる。それこそがカレドニアンGCのゴルフコースに対する理想と情熱の証でもあった。それは誕生までの歴史が物語っている。

 オーガスタの13番をイメージした名物15番(パー5)。
オーガスタの13番をイメージした名物15番(パー5)。4月末からはツツジが咲き乱れて美しさも際立つ
「日本にも世界レベルのコースを誕生させて質を高めたい」と早川治良会長
カレドニアンGCが誕生したのは、今から約30年前の1990年(平成2年)。まだバブルの余韻が残る時代である。それ以前の日本のゴルフはバブルに憑かれた時代だった。ゴルフコース建設は金儲けの手段。投資目的の会員権販売が優先し、コースの質は二の次。おまけに企業は、ゴルフ場を待合室代わりに利用し、接待ゴルフに血道を上げる。やさしく回れることで接待相手を喜ばせようという安易な発想。まさに粗製乱造の時代である。
そんな時にカレドニアンGCは誕生した。コースが完成したときには奇異の目で見られたものだ。それまでの日本のコースと比べ、見たこともない光景が展開する。大波のように大小のマウンドが連なるフェアウェイ。深いバンカーがいたるところに待ち受け、全英オープンなどでしか見たことがないポットバンカーがポッカリ口を開けるホールもある、池やクリークが行く手を遮り、一つとして、気の休まるホールがない。
特筆すべきはグリーンである。当時は1人でも多くの客を入れる目的もあって日本の大半のコースがゴルフコース本来の姿から外れた2グリーンが主流の中で、欧米と同じ1グリーンが異彩を放つ。幾つものマウンドを重ねたような複雑なうねりや段差があり、ホールによってはその傾斜でボールがバンカーやハロウ(窪地) 、グラスバンカー、池、クリークに転がり込む。まるで小さな小山を幾つか重ね合わせたように複雑で変化に富み、形状も様々。横長、縦長、斜め、砲台と18ホール一つとして同じ形状はない。
それまでの日本のコースにはない「レダン」(スコットランドのノースベリック15番ホールが起源で、右手前から左奥にかけて45度の角度で配置するグリーン)「グランドレベルグリーン」(人工的ではなく、自然のマウンドの上にグリーンを置く。周囲と一体になった造形で、見た目の自然さと共に様々なアプローチの技術を必要とする=オーガスタ・ナショナルに代表される)「アルプス」(グリーンの手前一部をセミブラインドの丘にし、ショットの想像力を高める)「フォールアウェイグリーン」(後方部が下がったグリーンで、落としどころを間違えればボールは止まらずに奥に転がり出る)など、世界の名コースに見られる伝統的な設計手法を各ホールやグリーンに施してある。受けグリーンが多く、単調な日本のコースとは、まるで異次元の世界が展開する。これに前述した超高速が加わるのだから、そのスリル、面白さは格別である。
 S字型に曲がる6番(パー5)グリーンの難度は世界トップレベル
S字型に曲がる6番(パー5)グリーンの難度は世界トップレベル
「天・地・人」が重なり合った運命的なコース誕生の秘話
ゴルフコースの良否を決めるのは一重にオーナーの力量にかかっている。不思議なことに、確固たる理念、知識、強い意志などがあるとそれに付随して、様々な要件が近づいてくる。俗にいう“天”“地”“人”だろうか。
マスターズの会場オーガスタ・ナショナルが誕生した背景には、ボビー・ジョーンズが前人未踏のグランドスラムを達成する前年の1929年、ペブルビーチGLでの全米アマに借敗、そのまま帰らずに近くのサイプレス・ポイントGC(常に世界のトップ3に位置する米国の名コース)でプレーすることにした。コースをプレーして「ここはパーフェクトだ」と感銘を受けたその時、偶然コースに設計者のアリスター・マッケンジーがいた。
すでに理想のコース建設の構想を描いていたジョーンズは、すぐさまマッケンジーと言葉を交わし、翌30年グランドスラム達成で引退した後、マッケンジーにコース設計を依頼、そして南部ジョージア州のオーガスタに眠っていた古い果樹園を発見、「こここそ、私を待っていた理想の地」と決めてあのオーガスタ・ナショナルを建設し、マスターズの誕生につなげている。
まさに神の意志が働いたとしか思えない運命的な出会い。カレドニアン誕生もまたそんなストーリーがあった。バブルに浮かれ、凡庸なコースが乱立する中で、当時の早川治良社長(現取締役会長) は、「このままでは日本のゴルフが世界から取り残されてしまう。未来のためにも、歴史に恥じないコースを造るためにも、今何かをしなければ手遅れになる」と決意。そんな時、日頃から敬愛し、交流のあった摂津茂和氏(明治2年~昭和63年、ゴルフ史家、世界ゴルフ大観を始め多くの著書がある)の顔を思い浮かべた。建設に当たって早川氏はまず摂津氏の自宅を訪ねた。自宅には欧米のゴルフ関連書籍が約2万冊近くあり、改めてその知識、造詣の深さに驚嘆する。
 複雑な傾斜で、奥が下がる最高に難しい9番ホール
複雑な傾斜で、奥が下がる最高に難しい9番ホール
 レダンホールで正確なショットが要求される17番(パー3)
レダンホールで正確なショットが要求される17番(パー3)
「世界基準のコースを何とか造りたいのですが」という早川氏の相談に、摂津氏は答える。「ゴルフを知りたかったら、その原点であるスコットランドのリンクスを見てきなさい。リンクスを知らずして、ゴルフを語る資格はありません」
この言葉に我が意を得た早川氏はすぐさま行動を起こす。1984年(昭和59年)ゴルフの聖地スコットランドからイングランドに至る巡礼の旅である。R&A(ロイヤル・エンシェント)のあるセントアンドリュース・オールドコースを始め、全英オープンなどで知られる名門コースをつぶさに見て回った。
その結果たどり着いたのが「ゴルフは自然と人間との闘い。そこにゴルフの魂がある」との結論である。この巡礼にはカレドニアンGCの理念を築く重要な出来事があった。
摂津氏に紹介状を書いてもらったスコットランドの名門の一つロイヤル・トルーンGCを訪れた時だった。理事長室に案内された早川氏はその部屋に飾られている1枚の額が目に留まった。そこには「TAM ARTE QUAM MARTE」の文字が飾られていた。
日本語に訳すと「力とともに知略も」の意味。これはラテン語で古代ローマ軍の戦闘用語で「力だけでなく、頭脳を用いる」の意味。これを「ゴルフは単に力でコースをねじふせるのではなく、自然を敬い、知略を用いるもの」との意味として、ロイヤル・トルーンが標語に採用したいきさつがある。
「これこそゴルフに通じる深遠な言葉だ。ぜひ新設するコースのモットーにしたい」と天啓に打たれた早川氏は、すぐさま同クラブのセクレタリーに懇願し、使用許可をもらっている。以来この標語はカレドニアンGCの魂となった。ちなみにカレドニアンの名称はスコットランドを意味する古語。モットーもコース名もすべてはリンクス魂へのこだわりである。
もう一人カレドニアンGCの誕生に欠かせない人物がいる。この摂津氏の弟子筋に当たり、当時高名なゴルフジャーナリストで、その後にコース設計家になった金田武明氏だ。早川氏はこの氏にも相談している。アーノルド・パーマーやジャック・ニクラスなど世界の名プレーヤーと交流を持ち、世界的なコースの事情に精通する金田氏は早川氏からの相談にこう答える。
世界基準のコースは1グリーンという金田武明氏の助言
「リンクスを含め、世界基準のコースは1グリーン。出来れば6枚から8枚の蓮の葉を重ね合わせたような起伏と変化に富んだものが理想。それがゴルフを無限に奥深くし、知性の高いものにする」
摂津氏、金田氏の共通の意見は「ゴルフコースの性格は一にパッティンググリーンの構造にかかっている。グリーン以外のティインググラウンド、ハザード、フェアウェイ、ラフなどはみんなアクセサリーにすぎない」
カレドニアンGCがグリーンを中心にレイアウトされ、更に14フィートにチャレンジするコンセプトの根源がここにあった。そして設計に当たって金田氏が強く推したのが、米国のJ・M・ポーレットである。ポーレットは米国設計家の第一人者ロバート・トレント・ジョーンズシニアに師事し、世界的な設計家として世に出ている。その特徴は、ハリー・コルト、チャールズ・アリソン、アリスター・マッケンジー、師のジョーンズらから流れるリンクスを基調とした作風にある。
前述した様々な伝統的設計技法がカレドニアンGCに数多く見られるのは、リンクスが原点であり、これに近代的な戦略性が加味されているからである。だからカレドニアンGCは「モダンクラシック」として、米国に生まれた作風を日本でも誕生させた類い稀なコースでもあるのだ。
ポーレットの設計の特徴は、“対角線”(ダイアゴナル設計ともいう)の設計にある。カレドニアンには一つとして同じ形状のグリーンもホールもないが、各ホールでこの対角線設計を取り入れている。
日本の多くの凡庸なコースに見られるフラットで、グリーンがホールと対面して攻略が単調になるのと違い、グリーンやフェアウェイを斜めに置いて対角線にすることで、プレーヤーの技量、球筋によって何本ものルートが生まれ、これがプレーを限りなく奥深くし、戦略性を高めている。日本アマ6回優勝の不滅の名プレーヤー中部銀次郎氏が現役を退いた後、初めてカレドニアンGCをプレーしてこう評している。
「見たこともない強いアンジュレーションのグリーン。巨大なバンカー、波頭が打ち寄せるようなフェアウェイを見ると、私を含め、日本人の規格外のゴルフを要求される。だから日本選手が外国試合で勝てない理由がわかりました」と感嘆したのも、日本のコースにない対角線デザインの重要さ、面白さに憑かれたから。以後中部氏はカレドニアンに惚れ込み、ホームコースのように頻繁にプレーするようになった。
世界の主流“対角線”デザインがコースのグレードを上げる
対角線デザインの代表ホールはカレドニアンのアーメンコーナーといわれる13番から始まっている(アーメンコーナーは実は12番からという評価がある)。16番はバックティーからでも343ヤード、ホワイトティーなら330ヤード、パー4と短い。ところが左サイドはマウンドが連なるラフで、200ヤードほどから先が落ち込み、ここも複雑なマウンドの小さな谷。第2打は軽い打ち下ろしで、グリーンは小さめの砲台で、左手前から右奥にかけて細長で斜めに位置している。右手前には深いポットバンカーが口を開ける。左サイドや前方のラフに入れれば例えウェッジのショットでも、脱出するのはひと苦労。ベストルートはフェアウェイ右サイドの平らなポジションにレイアップ(飛ばし屋なら)。そこからピンの位置でクラブを選定し、ショットを打ち分ける。右奥と、左手前のピンでは使うクラブも、距離感も大きく違う。まさに対角線のリンクス風難ホールだ。
17番はバックティーから195ヤードのパー3ホール。軽い打ち下ろしで、右手前から左奥に斜めにやや逆くの字に細長く、複雑なうねりのある2段グリーン。左サイドは深く切れ込んだ谷でグリーンにへばりつくように深いダブルバンカー、右にはやや深めのグラスバンカーがある。恐怖のあまり、体が止まり、左のバンカーに入れれば、万事休す。さりとて逃げて右のグラスバンカーに入れればよほどのアプローチ巧者でもカップに寄せるのは至難の業。ここもピンが手前と奥では1番手から2番手は違う。いわゆるレダンの典型的な対角線ホールだ。
対角線ホールの象徴は最終18番ホール。バックティーから555ヤード、レギュラーなら515ヤードのパー5ホール。ティーイングエリアの正面とグリーン手前には大きな池が横たわる。 そして池の周辺は白く輝く砂が美しいビーチバンカーがある。フェアウェイの随所にはポットバンカーが待ち構え、点と点をつなぐ難ホールだ。ここはティーショット、グリーンを狙うショットがすべて対角線の設計。
まずティーショットは前方の池とビーチバンカーを越すか、或いは左のフェアウェイに迂回するかの選択を迫られる。池越えでも最深ルートの右サイドを狙うなら270ヤード以上のキャリーが必要。中央のルートでも230ヤード以上のキャリーを必要とする。斜めに位置する池は対角線。無難な左のフェアウェイなら、第2打はともかく、第3打まで大きいクラブが必要になる。
うまく池を越せれば、それほど飛ばない人でも第3打ショートアイアンで打てるが、ここからが厄介。グリーンは左手前から右にカーブし、複雑なうねりのある大きな横長形状。手前は池と前方が小高い丘のビーチバンカーが待ち構える。ここも池は斜めで、ピンが右サイドに切ってあれば、池越えの高くて止まるアイアンショットが必要。オーバーすれば確実にバンカーに入る。
一方このプレッシャーを避けて左に逃げれば、とてつもなく長いパットか、或いは距離のあるアプローチショットが残る。ここはプレーヤーの技量、飛距離、球筋で何通りものルートが要求される美しくて難度の高いフィニッシングホールとして知られる。
順序が逆になったが、アウト2番は40メートルはある細長くて大波のような3段グリーン(パー5)、6番(パー5)はS字状に曲がりくねり、右サイドが大きな池。グリーンはというと低いところでは人間の腰から下が隠れてしまうような高低差の複雑なグリーンで、ピンが下で上に付ければ、傾斜とスピードで外にこぼれ出てしまうほどの難グリーン。
またほぼ90度右にカーブし、18番と共有する大きな池のある名物ホールの13番(パー4)は、池越えのショートカットか、無難に左へ逃げるかで、決断を迫られるホールである。ここは世界100選コースの選考委員が「短めのパー4ホールとしては世界の名ホール」と評価しており、あのペブルビーチGLの第2打海越えの8番との比較もある。
オーガスタ・ナショナルの名物13番ホール(パー5)をイメージした池とクリークが戦略性を高める15番(パー5)と共に、カレドニアンGCを代表するホールでもある。全編こんな調子でリスク&リウォード(危険と隣り合わせの報酬) による巧みなレイアウト。攻めるには勇気と技術が必要だが、そのスリル、決断がゴルフを限りなく高度で面白いものにする。だが各ホールとも個性があり、メモラビリテイ(記憶度)は抜群で、18ホール全体のバランスが素晴らしく、見事にハーモナイズされている。
ただ難しいだけではない。ホールはアベレージゴルファーも楽しめるように、技量に応じてのルートもあり、カレドニアンGCがあらゆるゴルファーに人気があるのは、欧米の設計思想「ゴルフはあらゆるゴルファーが楽しめなくてはいけない」という本当の意味の戦略性をポーレットもまた踏襲しているからでもある。
確固たる理念があれば、同じような理念を持った人間や条件が集まる。早川氏の思いが、摂津氏、金田氏、ポーレットを引き寄せ、そして理想的なゴルフ場の地が現れる。まさにオーガスタ・ナショナル誕生のような不思議な因縁がこのカレドニアンGCでも起きていたのだ。
良いコースとは、哲学や優れた設計だけでは成り立たない。そのコースを万全に仕上げる整備や、芝の育成があってはじめて完全な作品となる。
「人間革命」で実現したイノベーション
カレドニアンGCの精緻なメインテナンスを除いて同コースは語れない。ここに管理の努力の結晶が最後の仕上げとして登場する。
その先頭に立つのが、開場当時からグリーン管理に携わっている石井浩貴キーパー(現常務取締役グリーンキーパー)である。石井キーパーは「カレドニアンGCを世界レベルのコースに仕上げる」という早川会長の陣頭指揮のもとに、管理スタッフと共に、あらゆる研究・努力を重ねてきた。
コース内にナーセリーを作り、コースに適した芝を植えてテストや研究をする。当初は管理棟の近くのナーセリーで14種類もの芝の育成・研究を始め、その後15番と16番の歩経路横に現在のナーセリーを建設。ここで最終的に6種類ほどの芝に絞る。開場からこれまでペンクロス→グランプリ→オーソリティ→と変遷、そして14フィートへ の挑戦でこれまで日本ではほとんどお目にかかれない「Tyee」(タイイ)を選んでいる。真夏の極限テストでタイイが日本の酷暑に最も耐え、病気にも強い。また芝根も強く、葉が細かく、垂直に立ち、最小限の刈り高に耐えて理想的な転がりを可能にするなど新しい発見をしている。14フィートという日本では未知の世界に突入したのもこうした努力がその背景にある。
科学的メインテナンスへ
「不可能を可能にする」それがカレドニアンGC管理部のモットーだが、早川会長は、「日本にない高品質のグリーンを実現するには、まず人間革命」をスローガンに掲げ実現に取り組んだ。
その根幹となったのが「経験的(漠然的)メインテナンスから科学的(合理的)メインテナンス」への移行である。自身も含めて、スタッフに対し、「研究・工夫・実験(テスト)・分析・記録・最適化探求」の貫徹と、今後のためにその経過をアルバム化するなど、それまでの日本のメインテナンスにない近代化対策を講じ、それを浸透させた。
不可能を可能にした早川会長の信念
「何事も、現状に満足しては新しいものは出来ません。今まで誰もやっていないことに挑戦する。そこに人間の英知があります。ただしそれを実現するには、上からの指示に従うだけでは駄目です。スタッフ一人一人が自分自身の観察力を養い、問題点と解決法を考察し実行する“自立”と、自分を磨き、やるべき仕事について深掘りする“研究”。より良い方法や、手段がないかと自分の頭で考えてそれを実行する“工夫”。一人一人のこうした自覚と、蓄積が大きなパワーとなって不可能を可能にすると私は信じています」
この指導が管理スタッフに浸透した。前述石井キーパーは14フィートへの挑戦をこう述懐する。
「早川会長からこの指示を受けたとき、正直不可能ではないかと思いました。14フィートなどは日本では前例がありませんし、その技術もありません。芝の育成だけで経験のないスピードを出すのは、現状では不可能と思いました」
だが早川会長の指導はそれを上回る。「人間の智恵に不可能はない」と、石井キーパーとスタッフに檄を飛ばし、未知の世界に挑戦する気概を持たせる。
その結果、研究・実験を繰り返し、適切な芝を発見し、メンテナンス器具を改良し、芝床を見直し、エアレーションを毎月1回以上実施し、毎週全ホールのグリーンの表面から20㎝ほどの砂床をサンプリングし、芝草の細根が健康に育っているか、枯れ死した根が絡まって密集した層の透水性などの調査や不整箇所の改善など、あらゆることに取り組んだ。ローラーで芝を押しつぶして対処療法的にスピードを出すのではなく、あくまで良質な芝の育成でスピードを出す。つまりは芝とゴルフ場への愛情である。
そうした取り組みで、カレドニアンGCは、日本のコースでは不可能とされた刈り高2.8ミリを実現。だがここでも現状に満足しない。実は更に新種の芝を見つけ、刈り高も2.7ミリに挑戦するというプロジェクトに取り組んでいる。
四季を通しての高速グリーンの常態化は難事業
これが実現すればカレドニアンGCは、日本はおろか、世界でも例のないスピードの高品質グリーンが誕生することになる。ゴルフコースはオーナーの哲学と、キーパーの力量で、芸術性にまで高まることを立証しているカレドニアンGCの例。これまで同コースは、男子国内メジャーの日本プロ選手権(2000年)を始め、男子シニアツアー、女子レギュラーツアー、2017年には三菱ダイヤモンドカップなど多くのプロトーナメントや、アマチュア競技など数多くを開催してきた。その度にコースのグレードの高さがクローズアップされ、評価を高めてきた。300ヤード時代の現代に合わせ、ティーイングエリアを拡張するなど様々な改良に努力し、常に時代に合わせ進化を遂げている。
名コース(難コース)は、「ゴルフを限りなく豊かにし、知性高いものにする」――
早川会長の理想が、カレドニアンGCで見事に花を開きつつある。
『ゴルフスタイル』VOL.104より
 二人三脚の早川会長と石井キーパー
二人三脚の早川会長と石井キーパー
 高速グリーンのための砂散布
高速グリーンのための砂散布
 現在は2.7ミリカットに挑戦
現在は2.7ミリカットに挑戦